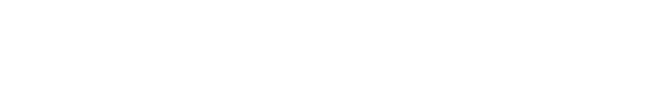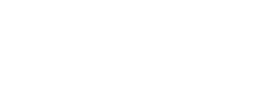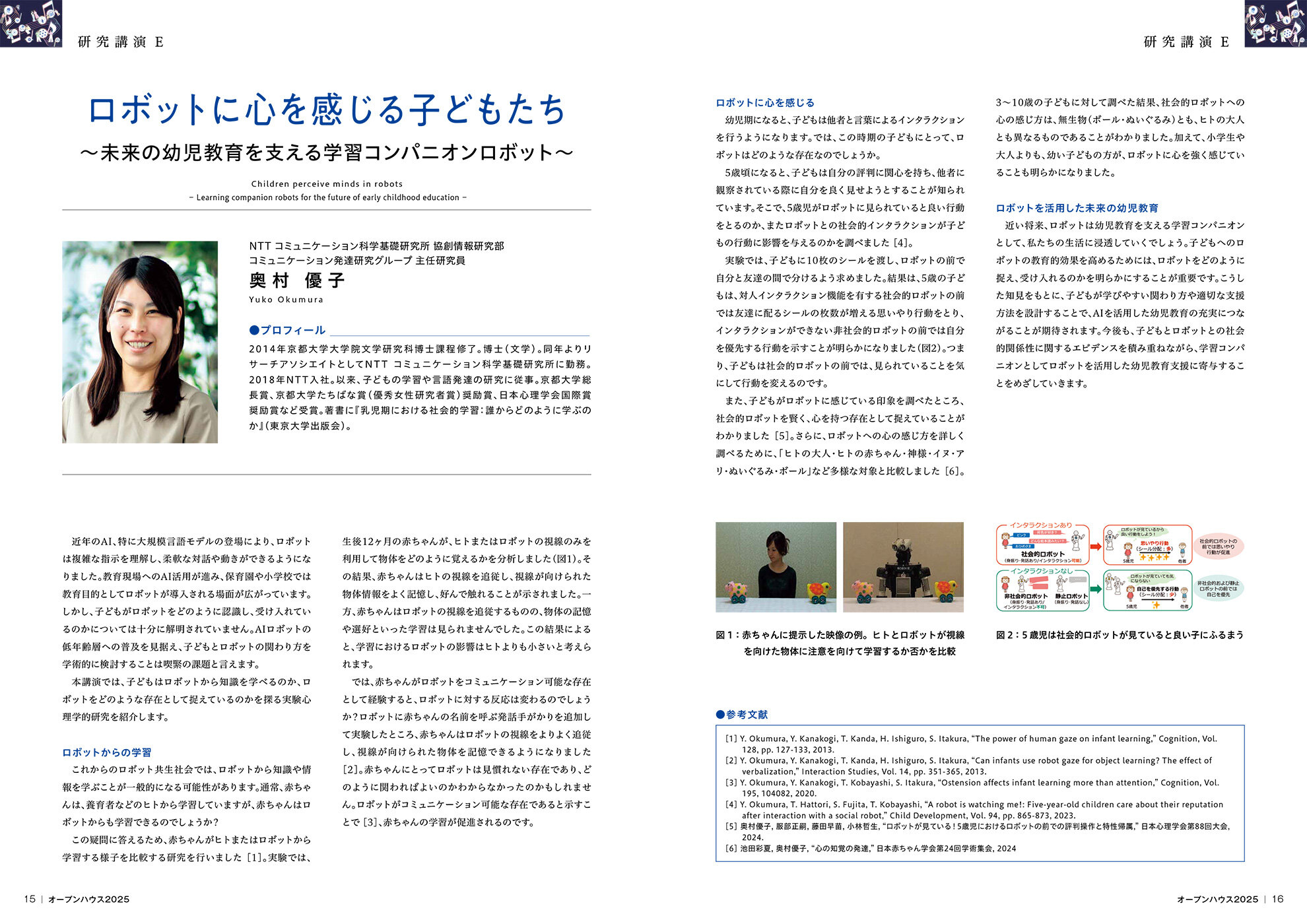ロボットに心を感じる子どもたち
未来の幼児教育を支える学習コンパニオンロボット
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 協創情報研究部 コミュニケーション発達研究グループ 主任研究員
奥村優子
奥村優子
技術の進展により、ロボットが子どもの生活に関わる機会が増えています。近い将来、ロボットは幼児教育を支える学習コンパニオンとして、私たちの生活に浸透していくと考えられます。しかし、子どもがロボットをどのように認識し、受け入れているのかについては十分に解明されていません。本講演では、子どもがロボットから知識を学べるのか、ロボットとの社会的インタラクションが子どもの行動や心の感じ方にどのような影響を与えるのかを探る実験心理学的研究を紹介します。
関連文献
[1] Y. Okumura, Y. Kanakogi, T. Kanda, H. Ishiguro, S. Itakura, “The power of human gaze on infant learning,” Cognition, Vol. 128, pp. 127-133, 2013.
[2] Y. Okumura, Y. Kanakogi, T. Kanda, H. Ishiguro, S. Itakura, “Can infants use robot gaze for object learning? The effect of verbalization,” Interaction Studies, Vol. 14, pp. 351-365, 2013.
[3] Y. Okumura, Y. Kanakogi, T. Kobayashi, S. Itakura, “Ostension affects infant learning more than attention,” Cognition, Vol. 195, 104082, 2020.
[4] Y. Okumura, T. Hattori, S. Fujita, T. Kobayashi, “A robot is watching me!: Five-year-old children care about their reputation after interaction with a social robot,” Child Development, Vol. 94, pp. 865-873, 2023.
[5] 奥村優子, 服部正嗣, 藤田早苗, 小林哲生, “ロボットが見ている!5歳児におけるロボットの前での評判操作と特性帰属,” 日本心理学会第88回大会, 2024.
[6] 池田彩夏, 奥村優子, “心の知覚の発達,” 日本赤ちゃん学会第24回学術集会, 2024

奥村優子
2014年京都大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。同年よりリサーチアソシエイトとしてNTTコミュニケーション科学基礎研究所に勤務。2018年NTT入社。以来、子どもの学習や言語発達の研究に従事。京都大学総長賞、京都大学たちばな賞(優秀女性研究者賞)奨励賞、日本心理学会国際賞奨励賞など受賞。著書に『乳児期における社会的学習:誰からどのように学ぶのか』(東京大学出版会)。